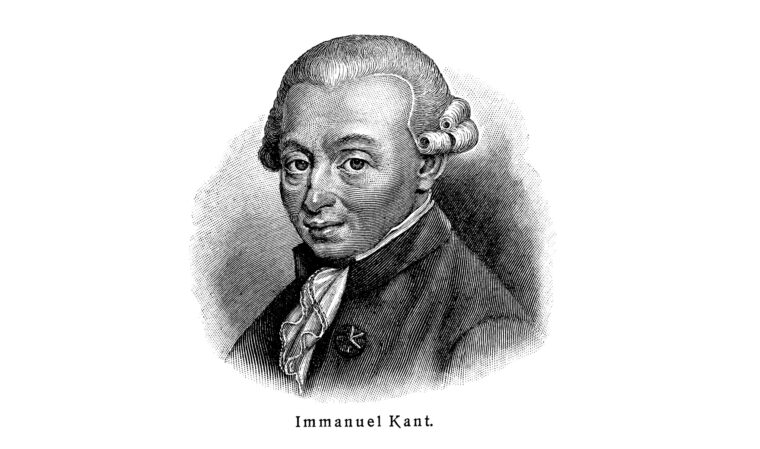
以前、永井経営塾のゲストライブで『獺祭』の桜井博志会長と対談した時のお話です。
獺祭は「お客様においしい酒を届ける」と考えています。
「儲けるため」とか「会社のため」といった条件は、一切抜きです。
獺祭は「お客様においしい酒を届ける」ために、常識外れの挑戦を数々行っています。
■杜氏に頼らない酒造り
獺祭は「お客様においしい酒を届ける」ために、純米吟醸に徹底してこだわりました。そしてこだわりすぎた結果、杜氏が反発して、全員辞めてしまいました。普通だったら、日本酒造りができなくなるのでここで妥協するところです。しかし「お客様においしい酒を届ける」ことに徹底してこだわった獺祭は、杜氏に頼らずに、自分たちで徹底してデータを取り、発酵室を常時5度で維持するなどの工夫をして、おいしいお酒が作れるようになりました。さらに杜氏の「冬に仕込む」という常識も見直した結果、通年で美味しい酒が作れるようになりました。
■酒屋への直売
こうして獺祭は人気で品薄になりました。すると転売ヤーが登場して獺祭を買い占め、価格が高騰するようになりました。これでは獺祭が目指す「お客様においしい酒を届ける」ことができません。それまで日本酒業界では、酒屋(小売店)には問屋経由で卸すのが常識でした。そこで獺祭は問屋に「仕入れを増やして欲しい」とお願いしましたが、問屋は「他の日本酒もあるし平等にしなければいけないからダメ」と言って仕入れを増やしません。そこで獺祭は、日本酒業界では常識外れとなる「酒屋への直販」を開始しました。
獺祭はひたすら「お客様においしい酒を届ける」ために、こうした挑戦を次々と行いました。
桜井博志会長の社長就任時は1984年。社長退任までの2016年で、日本酒業界の市場規模は1/4に縮小しました。しかしこの間に、獺祭は売上100倍以上に成長したのです。
獺祭は次々と障害にぶつかりましたが、無条件で「お客様においしい酒を届ける」を首尾一貫して徹底した結果、市場が大きく縮小する逆風の中、長期的な信頼やブランド力を確立したのです。
この獺祭の挑戦、実に骨太ですよね。この獺祭の考え方を読み解くヒントが、実は西洋哲学の中にあります。
それはカント哲学です。
哲学というと「難しそうだし自分には関係ないなぁ」と思いがちですが、実は哲学はそんなに難しいことは言ってません。むしろ、私たちの身近な問題に対して、本質的にどう考えれば良いのかというヒントを教えてくれます。
カントは、「我々はどのように考え、どのように行動すべきか?」を考え抜きました。
そこで人間の行動原則を決める考え方としてカントが提唱したのが、「定言命法(ていげんめいほう)」と「仮言命法(かげんめいほう)」という考え方です。
【定言命法】
条件なしの行動原理。たとえば「ウソをついてはダメ」
【仮言命法】
条件付きの行動原理。たとえば「バレるから、ウソをついてはダメ」
仮言命法の「バレるから、ウソはダメ」だと、「ばれなきゃウソはOK」となりますよね。これはちょっと問題がありそうです。バレなければ、世の中はウソつきだらけ。正直者が損をしてしまいます。
そこでカントは定言命法で「(無条件で)ウソはダメ」と考えるのが正しい、としました。
この定言命法は、骨太なビジネスや自分の生き方を考える上で役立つのです。
「お客様においしい酒を届ける」という獺祭の考え方も、まさに定言命法です。「儲けるため」とか「会社のため」といった条件は、一切抜きです。
だから周囲の条件に左右されずに、自分の考え方や行動が首尾一貫するので、 長期的な信頼やブランド力につながるのです。
獺祭とは真逆の事例もあります。GAFAの一部です。
GAFAの多くは、長年企業理念に「多様性の尊重」を掲げてきました。しかしトランプ政権が「これまでのDEI施策はすべて見直し」という方針を出すと、GAFAの一部は、「多様性の尊重」をあっさりと企業理念から取り下げました。
残念なことに、彼らの企業理念は、条件付きの仮言命法だったのですね。
このように定言命法で考えることで、ビジネスが骨太になり、長期的に信頼されるブランドを確立できます。
ただ定言命法には限界もあります。
【定言命法の限界① 中身を問わない】
定言命法は形式しか見ないので、価値の中身が正しいか否かは問いません。
そこでナチスが利用しました。それが「ヒトラー総統が汝の行為を知ったとすれば是認するように行為せよ」という「第三帝国の定言命法」です。
ナチスは、「国家と民族の利益」を絶対原則に設定し、それを全ドイツ国民の義務としました。この結果、「ヒトラーの命令=法」となり、無条件服従を正当化したのです。
つまり定言命法を誤って使うと、価値の中身が歪んでも、形式だけで正当化できてしまうのです。
一時期の「企業価値最大化経営」を掲げて、株価を上げてひたすら時価総額アップのみに邁進してムリを重ねた企業の多くが、その後窮地に陥ったのも、その例です。
本来の定言命法は、「あなたの自分ルールが、他の全ての人にとって正しければOKだよ」という考え方です。
この「他の全ての人」を誰に設定するかが問題なのです。
「会社関係者」なのか、「全国民」なのか、「全人類」なのか、あるいは「地球にいるすべての生きとし生けるもの」なのか。
考え始めると、これはなかなか難しい問題です。
たとえば「地球にいるすべての生きとし生けるもの」と考えると、私たちの食生活自体が成り立たなくなってしまいます。
これは定言命法が自分ルールをベースにしているための限界なのです。
【定言命法の限界② 硬直性】
私は1984年に日本IBMに入社しました。IBMを選んだ理由は、IBMの企業理念に「個人の尊重」があったからです。IBMは1911年の創業以来、「個人の尊重」を80年以上徹底し、人員解雇は一切行いませんでした。
しかし1994年に経営危機に陥って会社の存続自体が危うくなると、IBMは初の人員削減を行いました。この時に人員削減を行わなければ、IBMはおそらく潰れてました。
定言命法で理念を絶対に守ると、こうした組織存続の危機に直面することがあります。
つまり定言命法のもう一つの限界は「例外を認めない硬直性」です。
では現実的に、ビジネスではどう考えればいいのでしょうか?
①まず定言命法は、基本的な考え方や理念が健全か否かを考える上でとても役にたちます。たとえば、その考え方が、社外でも共有できるかという視点で考えると、骨太な理念に育っていきます。
②ここで考えるべきは、「組織にいる一人一人のメンバーに、どのように行動して欲しいか」ということ。もともと定言命法は「個人の主観的な行動原理(自分ルール)で、普天的な善悪を判断しよう」という考え方です。
平野洋一郎さんが創業したアステリアの理念は「発想と挑戦」「世界的視野」「幸せの連鎖」です。
平野さんが主宰する早朝勉強会「経営730」で平野さんにお話しを伺ったところ、「組織にいる人たち一人一人がどう行動して欲しいか。さらに世の中にどのように貢献すればいいかを考えて、この理念を作った」とおっしゃっていました。
アステリアの理念は、まさに定言命法的に作られています。
③一方で定言命法を誤用すると、間違った方向で組織が一直線に進み、最後には破綻するリスクもあります。そこで多様な視点で、批判したり再検証できる仕組みが必要になります。
④硬直性も、定言命法の弱点です。過度に頑なにせずに、環境変化の応じて柔軟に、例外もある程度許すことも必要です。
③と④については、会社組織の場合、社外取締役によるガバナンスを効かせることも一つの方法です。
カント哲学というと「お堅い哲学」の代表ですが、現在のビジネスでも大いに役立つのです。
■当コラムは、毎週メルマガでお届けしています。ご登録はこちらへ。