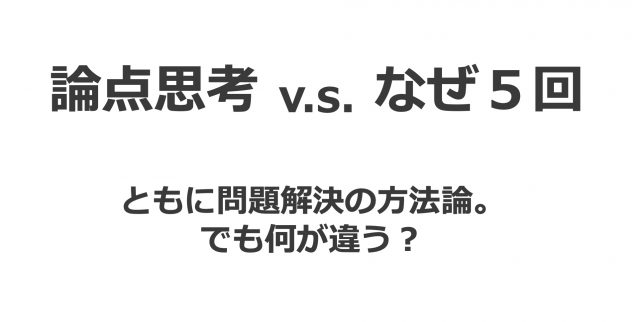
前回のコラムで、「論点思考」を紹介しました。おさらいすると、
・議論の際に、意見が発散することがある
・大きな理由の1つは。「何の問題を解決するか」が設定されていないから
・まず「解決すべき問題」の設定が大事。これが「論点思考」
・論点とは「解決すべき問題」のことで、必ず打ち手とセットである
・たとえば「昨晩泥棒が入った」のは現象。論点ではないので議論しても答えは出ない。
・「泥棒が入って損害が発生した」が論点で、「損害を算定し、最少化する」が打ち手
・論点は、置かれた状況で変わる
ということです。
ある企業様の研修でこの論点思考の説明をしたところ、こんなご質問をいただきました。
「よく『”なぜ5回”を繰り返して根本原因を特定せよ』って言いますよね。『論点思考』って、『なぜ5回』と何が違うんですか?」
これは大事なポイントなので、このコラムで皆様とシェアします。
「なぜ5回」は、トヨタが問題の原因追及の方法論として活用している考え方です。
たとえば「生産機械が止まった」という問題の場合、こう考えます。
❶「なぜ機械が止まったか?」→「過負荷がかかり、ヒューズが切れたから」
❷「なぜ過負荷がかかったか?」→「軸受部の潤滑が十分でないから」
❸「なぜ十分に潤滑しないのか?」→「潤滑ポンプが十分くみ上げていないから」
❹「なぜ十分くみ上げないのか?」→「ポンプの軸が摩耗しガタガタになったから」
❺「なぜ摩耗したのか?」→「ろ過器がついておらず、切粉が入ったから」
→対策:「ろ過器を付ける」
こうした対策を取れば、同じ問題の再発は防げますよね。
このように「論点思考」と「なぜ5回」は、使うべき場面が違うのです。
たとえば突発的なトラブルが起こって問題が拡大し続けているのに、「この根本原因は何なのだろう? なぜ5回で考えよう」と悠長にやっていると、業績は悪化し続けるばかりです。
こんな場合は迅速な対応が必要なので、状況悪化を食い止めるためにいくつかの論点を素早く見極め、優先順位を付けて、迅速に対策を取るべきですよね。
逆に、似たようなトラブルが何度も再発する現場は少なくありません。企業でも、同じような不祥事を何度も繰り返す企業があります。こんな場合は性急な問題解決に走らずに、再発防止を図るためにチームで知恵を出し合って「なぜ5回」を考え抜いて、根本的な対応策を考えるべきです。
このように、「論点思考」も「なぜ5回」も、ともに問題解決の方法論ですが、目的と適用する分野が異なります。まとめるとこうなります。
【目的】
・論点思考…効率的な意志決定のため、問題を正しく定義し、議論すべき論点を明確にする
・なぜ5回…再発を防ぐために、問題の根本原因を特定し、改善策を導き出す
【適用する分野】
・論点思考…経営判断、業務改善の優先順位付け、緊急な問題対応、議論の整理と意志決定
・なぜ5回…トラブルの再発防止、品質管理、業務改善
【よい点】
・論点思考…問題の全体像を短時間で整理し、ムダな議論を省き、意志決定スピードが向上する
・なぜ5回…根本原因に辿り着きやすく、問題の再発防止ができる。考え方がシンプル
【悪い点】
・論点思考…迅速な意志決定を優先するために、因果関係を分析せずに表面的な論点で留まり、根本原因を見落とすリスクあり
・なぜ5回…因果関係を過度に単純化すると誤った原因に辿り着くリスク。狭い視野になりがち
「論点思考」も「なぜ5回」も問題解決の道具です。
そして道具は万能ではありません。
クルマは移動の道具として万能に見えますが、自宅から徒歩2分のコンビニに行くには、クルマよりも徒歩という手段が優れています。遠い場所に行く時でも、天気が良く荷物も軽ければ、クルマよりも自転車の方がいい場合もあります。
問題解決の手段は色々とあります。それぞれの目的と性質を理解した上で、使いこなしたいものです。
■当コラムは、毎週メルマガでお届けしています。ご登録はこちらへ。