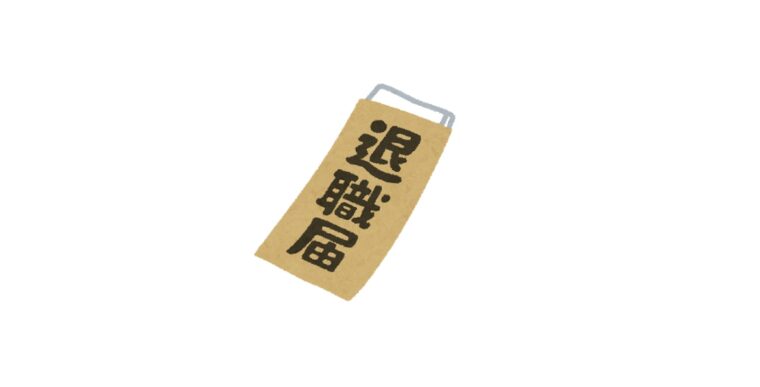
「最近のZ世代はすぐ辞める」「若者は転職が常識」とよく言われます。
これって本当でしょうか?
2025/4/12付の日本経済新聞の記事「早期離職率 今は昔も3割」は、この点を分析してます。
厚生労働省が2024年10月に発表した最新調査結果では、2021年3月に卒業した新入社員で入社3年以内に離職した人は34.9%でした。
人手不足の中で苦労して採用した新入社員が1/3以上も退職したら、会社にとって大損失です。
ただこれは、必ずしも高い水準とはいえません。
本記事によると、早期退職率は1995年卒で3割を越えてから、長期横ばいで推移し、過去最高は2004年卒業の36.6%。その後28〜36%の範囲で上下しています。
ただ残念ながら、本記事は直近の20年だけを考察しています。
実は若者の大量退職は、今に始まったことではありません。
社会人類学者の中根千枝先生が1967年に刊行した116万部の超ロングセラー『タテ社会の人間関係』と言う名著があります。本書の中で、中根先生はこう述べておられます
「因みに、近年増加したといわれる転職のケースをみると、その大部分が入社してまもない、たとえば二~三年内の若年層に集中している。彼らの場合は、まだ社会的資本の蓄積が低く、転職による損失が少ないためである」
少し補足します。
たとえばある会社に、新入社員が入社したとします。
会社に限らず日本の組織では、組織内で他のメンバーと接触した時間の長さが、その人が組織の中で使える社会資本となります。
つまり口にするかどうかは別として、「アナタよりボクはこの組織に10年長くいるよ。だからボクはちょっと偉いんだ。ヨロシクね」という状態になります。
日本人にとって、会社は擬似的な「イエ」なのです。
だから「何年入社組」とか「職場の先輩後輩関係」が極めて大事なのです。
さて新入社員は、組織内で他の人たちとの接触時間がゼロです。従って社会資本的には、最下層にいます。その後、勤続年数が増えるとともに、社会資本は蓄積されてます。この社会資本が、年功序列意識の源泉です。
でもこの社会資本は、別の会社に転職するとリセットされ、またゼロからの蓄積になります。
「日本人は組織への忠誠心が高く集団主義だ」といわれるのも、日本人がなかなか転職しないのも、こうした組織構造の中にいる個人が、合理的に行動した結果です。
そして大量の若者が早期退職するのも、社会資本の蓄積が少ない状態で組織から離れ、より自分に合った別組織に移動して社会資本を蓄積し直した方が、転職による損失が小さく抑えられる、と合理的に判断した結果なのです。
日本の「イエ制度」は戦後なくなりましたが、戦前の日本では「イエ制度」は当たり前だったので、この考え方は徐々に薄れつつ根強く日本社会に残り、これが若者の大量早期退職に繋がっているわけです。
とはいえ、苦労して採用した新入社員が大量に早期退職するのは、やはり困ります。でも上記のような背景がわかると、対応策も見えてきます。
そもそも日本の若者が「早期退職しよう」と考えるのは、「この組織で社会資本を蓄積しても、自分には損だ。他の組織に移って社会資本を蓄積した方がいい」と考えるからです。ですので対応策としては、
・自社を職場として魅力的に: 社員にとって自社が「ここは自分がキャリアを積み重ねる上で理想の組織だな」と思われる職場になるように、常に改善を重ねる。
とはいえ、人はそれぞれなので…
・就職前: 就活生と自社のマッチングでは、相性を重視し、かつ就活生の納得度を高める。さらに入社後の認識とギャップが起きないように、事前に「あるがままの社内」を隠さずに見せる。
とはいえ、どんな素晴らしい会社でも、現実には色々あるので…
・就活後: 納得して就職した新入社員でも、入社後はフォローを徹底する。
ということで、大量の若者が早期退職するのは、日本社会の構造的な問題です。それを踏まえた上で、有効な対応策を考えたいものです。
■当コラムは、毎週メルマガでお届けしています。ご登録はこちらへ。